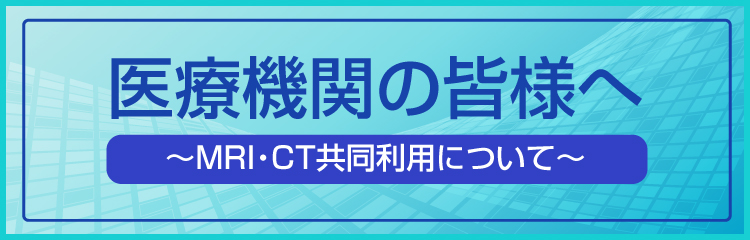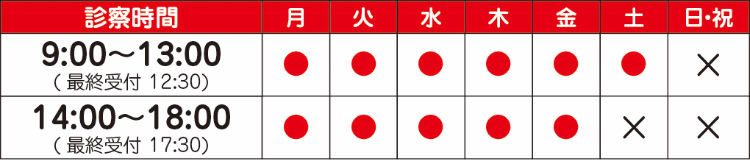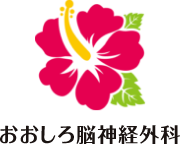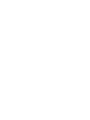福岡、宗像の脳神経外科「おおしろ脳神経外科」頭痛・めまい・認知症(物忘れ)・生活習慣病
MRIで見つかる脳疾患
脳ドッグでは、隠れ脳梗塞以外にどんな病気が見つかるの?
脳ドックは、脳に関する疾患の診断や疾患リスクの早期発見などを目的に、脳の断層画像を得るMRI検査と脳血管を立体的に描出するMRA検査をセットで行う検診コースの総称です。脳に関係する病気の治療を行うのではなく、受診した時点での「脳の健康状態」を把握することを目的としており、将来的な病気のリスクを評価しています。よく知られている脳梗塞や脳出血などの脳血管疾患は、突然発症してそのまま命を落とす不運なケースも少なくありません。また、発症後に一命をとりとめたとしても、体に麻痺や言語障害などの後遺症を残すケースも多く、一度の発症で人生を大きく左右する恐れのある病気です。このような脳疾患は自覚症状などの前触れがなく発症することも多く、一度病気を発症してしまうと取り返しがつかないことも多く、その発症を未然に防ぐことがとても大切になってきます。では実際に、脳ドックで使用されているMRI・MRA検査では、隠れ脳梗塞以外にどのような疾患が見つかるのでしょうか。
脳ドックで見つかる主な脳疾患
比較的よく知られている病気には未破裂脳動脈瘤や脳腫瘍がありますが、それ以外にも深部白質病変、脳血管狭窄症、さらには脳微小出血などがあります。最近では、脳ドックの検査項目に認知機能の精密検査を組み込み、認知症のスクリーニングも兼ねて実施している施設が多くなっています。通常、脳ドックで何らかの異常が見つかったとしても、すぐに外科的な治療を必要とするものは少なく、多くは内科的な投薬治療や画像による経過観察を行うことが大部分です。また、脳ドックを受けるもうひとつの利点としては、これまでの生活習慣を見直せる点があります。検診などで見つかった危険因子を日々の生活の中で見つめ直すことで修正し、将来的な脳血管疾患のリスクを低減できるきっかけにもなります。今回は、脳ドッグで使用されるMRI・MRA検査で比較的遭遇する機会があり、将来的にも重要な無症候性脳病変についても説明していきたいと思います
未破裂脳動脈瘤
脳動脈瘤とは、動脈の一部が瘤(コブ)状に膨らむ病気です。脳動脈瘤が破裂するとくも膜下出血を起こしますが、破裂する前の状態が未破裂脳動脈瘤となります。比較的大きな動脈瘤では、瞼が下がる(眼瞼下垂)、物が二重に見える(複視)などの症状を呈する場合がありますが、ほとんどの未破裂脳動脈瘤は破裂するまで無症状で経過します。脳ドックでは、日本人の約5%に未破裂脳動脈瘤が見つかるとも言われています。残念ながら、動脈瘤の壁は病的な構造をしていることが多く、少ないながらも出血(破裂)する危険性を有しています。もし破裂した場合は致死的なくも膜下出血になるため、MRIで未破裂脳動脈瘤が見つかった患者さんは、どうしても不安感を抱くことになります。しかし、多くの未破裂脳動脈瘤の破裂率はそこまで高くないため、すべての患者さんで治療を急ぐ必要はありません。但し、脳動脈瘤のサイズが大きい方や高血圧・喫煙歴・くも膜下出血の家族歴がある方などでは破裂のリスクが高くなりますので注意が必要です。
脳腫瘍
脳内にできる良性または悪性の腫瘍も初期段階では症状が現れないことが多々あります。しかし、腫瘍が大きくなると良性腫瘍でも脳や神経を圧迫して視覚障害、運動障害、言語障害などの症状が現われることがあります。一般に脳ドックで見つかる脳腫瘍は、髄膜腫、下垂体腺腫、神経鞘腫などの良性腫瘍がほとんどであり、まれに神経膠腫(グリオーマ)という脳実質から発生する悪性腫瘍が見つかることがあります。脳腫瘍が発見された場合には、腫瘍の種類や大きさ、部位などに応じて治療方針が決まりますが、小さな良性腫瘍ではほとんどが経過観察となります。但し、ある程度の大きさの脳腫瘍の場合には、年齢などを考慮して手術を検討することがあります。
大脳白質病変
大脳白質病変とは、脳深部の大脳白質(主に神経線維が存在する部位)に生じる加齢や生活習慣に関連する脳小血管病の代表的変化であり、脳血流低下などによる慢性的な虚血や血液脳関門の障害などによって生じると考えられています。長期間の血圧高値のため脳の細い血管は動脈硬化を引き起こし、栄養を送る血管の血流不足による変化をもたらします。最終的には血管外に水分が漏れ出して、MRIのFLAIR画像では「白いまだら状の模様」として映し出される病変を白質病変と呼びます。通常は加齢によっても起こる病変ですが、変化の程度が平均年齢よりも進行しているときには注意が必要です。患者さん自身にとっては無症状が多いのですが、白質病変が拡大していくと将来的な脳卒中や認知症のリスクが高くなることが知られています。特に脳室周囲の白質病変では歩行速度の低下に関連するとも言われ、さらに大脳深部や皮質下の白質病変は認知機能の低下に関与することが指摘されています。
無症候性脳血管狭窄症
無症候性脳血管狭窄症とは、頸動脈や脳の大きな血管(主幹動脈)が狭くなっているにもかかわらず、手足の麻痺や言語障害などの自覚症状がない状態を示す病気です。その大部分は脳ドックや他の検査時に偶然発見されることが多く、特に高齢者ではその頻度が高まります。もし症状がないからといってそのまま放置していると、実は将来的に症状を呈する脳梗塞や脳出血、あるいは認知症などにつながるリスクがあるため、適切な管理・対応が必要になることがあります。高血圧は最大の危険因子とされますが、それ以外にも糖尿病、脂質異常症、喫煙習慣なども管理すべき危険因子となります。また、狭窄度の程度によっては抗血小板剤やコレステロール値を適切に保つ脂質改善薬が推奨されたり、あるいは狭窄度が強い場合には神経症状がなくても外科的な治療が検討されることもあります。
脳微小出血
MRI撮像法の進歩によって発見されるようになった病変であり、これまでのCT検査では見つけられないものです。その本体は脳内の小さな血管が破れて、ごく少量の血液(ヘモグロビン)が血管外に漏れ出した痕跡を見ているものです。多くの場合は無症状であり、いつの間にか生じている病態で、加齢とともに発生頻度は高くなります。通常は高血圧が強く関連しており、健常者において微小出血痕がみられる頻度は約5%に対し、脳梗塞患者では約35%、さらに脳出血患者では約60%に出血痕が認められたと報告されています。大脳白質病変と同様ですが、微小出血巣も将来的には脳卒中だけではなく、認知症と関連することが指摘されています。もし、抗血栓薬(抗血小板剤や抗凝固剤)を使用している患者さんで、偶然にも脳微小出血痕が見つかった場合には、その出血のリスクを考慮して慎重な投与が必要になることがあります。
脳ドッグでも認知症の診断は可能ですか?
脳ドックでは、MRIやMRAといった検査法を用いて脳の構造や血管の状態を詳しく調べますので、脳梗塞や脳出血といった脳血管疾患の発見に役立ちます。このような脳血管疾患が血管性認知症の原因となるため、脳ドッグを受けることで血管性認知症のリスクを把握することができます。また、脳全体の萎縮や記憶を司る海馬の萎縮度も容易に確認できますので、アルツハイマー型認知症の兆候を見つけることもできます。しかし、認知症の診断においては、脳ドックで得られる形態的な情報だけではなく、医師による問診、身体検査、神経心理学的検査など、複数の検査を組み合わせて総合的に判断する必要があります。下記に示した追加検査などを行いながら、診断の手助けを行っています。
改訂長谷川式簡易知能評価スケール(HDS-R)
認知症の診断に用いられる認知機能テストのひとつで、日本の医療機関で多く使われています。年齢、見当識、3単語の即時記銘と遅延再生、計算、数字の逆唱、物品記銘、言語流暢性の9項目からなる30点満点の認知機能検査です。HDS-Rは20点以下で認知症が示唆されます。
ミニメンタルステート検査(MMSE)
世界で最も多く使われている認知症の検査法で、時間や場所の見当識、3単語の即時再生と遅延再生、計算、物品呼称、文章復唱、3段階の口頭命令、書字命令、文章書字、図形模写の計11項目から構成されています。30点満点中23点以下の場合は認知症の疑いがあり、27点以下だと軽度認知障害の疑いがあるとされています。
VSRAD(早期アルツハイマー型認知症診断支援ソフト)
MRI画像を使い海馬の萎縮を調べる検査で、あくまで脳の萎縮の程度を見る検査です。アルツハイマー型認知症の診断を行う検査法ではありませんが、診断の一助となります。さらに最近ではAI技術を活用し、医師の目だけでは見つけにくい、ごくわずかな萎縮も客観的な数値や画像で「見える化」できるようになっています。
脳ドックで病気が見つかったときは、どうしたらいいですか?
もし、脳ドックで「何らかの病気」が見つかったら、その種類や程度によって管理法や対策は異なりますが、主に以下のような点が挙げられます。
危険因子の管理
高血圧、糖尿病、脂質異常症といった生活習慣病は、脳卒中や認知症の重要な危険因子となります。これらの病気を持っている場合は、食事内容の見直したり(減塩)、適度な運動、禁煙、節酒などの生活習慣の改善が推奨されます。必要に応じて専門医と相談し、内服薬による治療を行うことも重要となってきます。
定期的な経過観察
すぐに治療が必要とならない場合でも、画像による経過観察が推奨されることがよくあります。これにより病変の進行状況を把握し、適切なタイミングで治療を開始することも可能となります。
専門医への受診
大きな未破裂脳動脈瘤や比較的大きな脳腫瘍が発見された場合には、やはり基幹病院への受診が強く勧められます。状況によっては低侵襲的な血管内治療や開頭手術などの予防的治療が検討されることがでてきます。
認知機能の評価
隠れ脳梗塞や大脳白質病変、あるいは脳微小出血などでは、将来的な認知機能に影響することが懸念されています。また、具体的な健忘・物忘れ、あるいは記憶力低下で直接相談に訪れる方もおられます。将来的な認知症へのリスクが懸念される場合には、定期的な認知機能検査や早期治療の導入も検討される症例がでてきます。
まとめ
脳ドックは、自覚症状が現れる前に脳の病気を発見し、将来の脳卒中や認知症のリスクを軽減することを目的とした予防検査と言えます。症状がなくともMRI検査で発見される無症候性病変の中には、後に後遺症を残すような面倒な病気を併発したり、厄介な疾病につながることも起こりますので、早期発見の意義は大きいと言えます。但し、無症候性病変の種類によっては管理法や対策も異なってきますので、病態や病状を的確に見極めることがより大切になります。どうしても、将来的な脳卒中や認知症のリスクについて不安がある方は脳ドックを受けてもらい、まずは現状を把握することが重要な予防策につながるものと考えられます。